シーズンが終わり、次のシーズンに向けての練習を計画する際、目標は立てたけれど、そこに向けてどのような練習をすればよいのか分からない、という方も多いでしょう。年間を通して同じような練習を繰り返していて、記録が伸び悩んでいる場合には、トレーニング計画に期分けをすることをお勧めします。目標レースから逆算して、それぞれの時期に合わせた目的を持つことで、メリハリのある練習ができ、大幅な記録向上が期待できるかもしれません。
ここでは、目標レースに向けて3つの時期に分けたトレーニング計画をご紹介します。これを実践することで、どの時期に「何を鍛えるべきか」が明確になり、効果的な練習が行えるようになります。
・「いつ」「何を」鍛えれば良いかが分かる
皆さんのトレーニング計画に活用してみてください。
*練習例として記載しているペースは全て1kmあたりになります。
一般期
この時期は、主要なレースが終わり、次のシーズンに向けて体づくりを始める時期です。坂ダッシュやドリル練習、ファルトレクなどを取り入れ、さまざまな刺激を体に与えていきましょう。急に走る距離を増やすと故障の原因となるため、少しずつ距離を増やしていきます。
この時期は通常、4週間程度が目安ですが、前のシーズンから練習を継続している場合は省略したり、短縮することも可能です(本来はシーズン終了後に2週間程度の完全休養を設けることが望ましいです)。
練習例
- 13~16kmをレースペースより30秒遅いペースで
- 8~10kmをレースペースより20秒遅いペースで
- 1~3分のファルトレク(レースペース~レースペースより15秒速いペースで自由に時間を組み合わせる)
- 60mほどの坂ダッシュ
準備期
この時期は、想定するレーススピードやレースに必要な持久力をサポートするための練習を行う時期です。レースペース以上のスピードでの練習や、レースペースより少し遅いペースで長い距離を走る練習が中心となります。
期間としては4~6週間程度で、この時期にしっかりとスピードを出せる体を作ることで、レースペースに余裕を持って移行できるようになります。強度が上がる時期なので、ケアを十分に行い、故障を避けるようにしましょう。
練習例
① レーススピードを支えるスピードの開発
- 5×300mをレースペースより20秒速く(2~3分のウォーク)
- 2×6×500mをレースペースより10秒速く(1分のウォーク~ジョグ、セット間は5分のウォーク~ジョグ)
1000mまでの距離でレースペース以上のスピードを出す練習を行いましょう。
② レースに必要な持久力をサポートする持久力の開発
- 6×1200mをレースペースより5~7秒遅く(リカバリーは400mをレースペースより30秒遅いペースで)
- 12kmをレースペースより20秒遅いペースで
一般期よりも走る距離を徐々に増やしていき、リカバリーを速くするインターバル形式の練習を行い、心肺機能を鍛えます。この練習は非常に効果的です。
特異期
この時期は、レースを意識した練習が中心となります。レースペースで走る練習や、レースペースより少し遅いペースで長い距離を走る練習が中心となり、準備期でしっかりと練習が積めていれば、スムーズに移行できます。
練習例
① レースペースの練習
- 4~5×2000mをレースペースで(リカバリーは3~4分のジョグ)
- 6×1000mをレースペースより10秒速いペースで(リカバリーは2~3分のジョグ)
レースペースと同じ、または少し速いペースでのインターバルトレーニングを中心に行いましょう。準備期よりもスピードは落ちますが、距離が伸びます。
② レースに必要な持久力の開発
- 16kmをレースペースより20秒遅いペースで
このように、各時期をおおよそ4週間ずつサイクルで実施することで、16週間かけて競技に合わせた体力を養うことができます。これまでのトレーニング状況によって、一般期を減らしたり、準備期を増やすなどのアレンジも可能です。
今回紹介した期分けの方法は、レナート・カノーバが用いている方法です。レースペースよりも離れたスピードから始め、徐々にレースペースに近づけていきます。それぞれの時期に開発する能力を明確にして取り組むことで、練習に意味を持たせることができます。
年間を通して同じ練習をしている方は、目標にする大会から逆算して、期分けトレーニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。
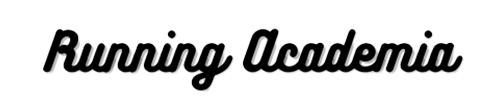
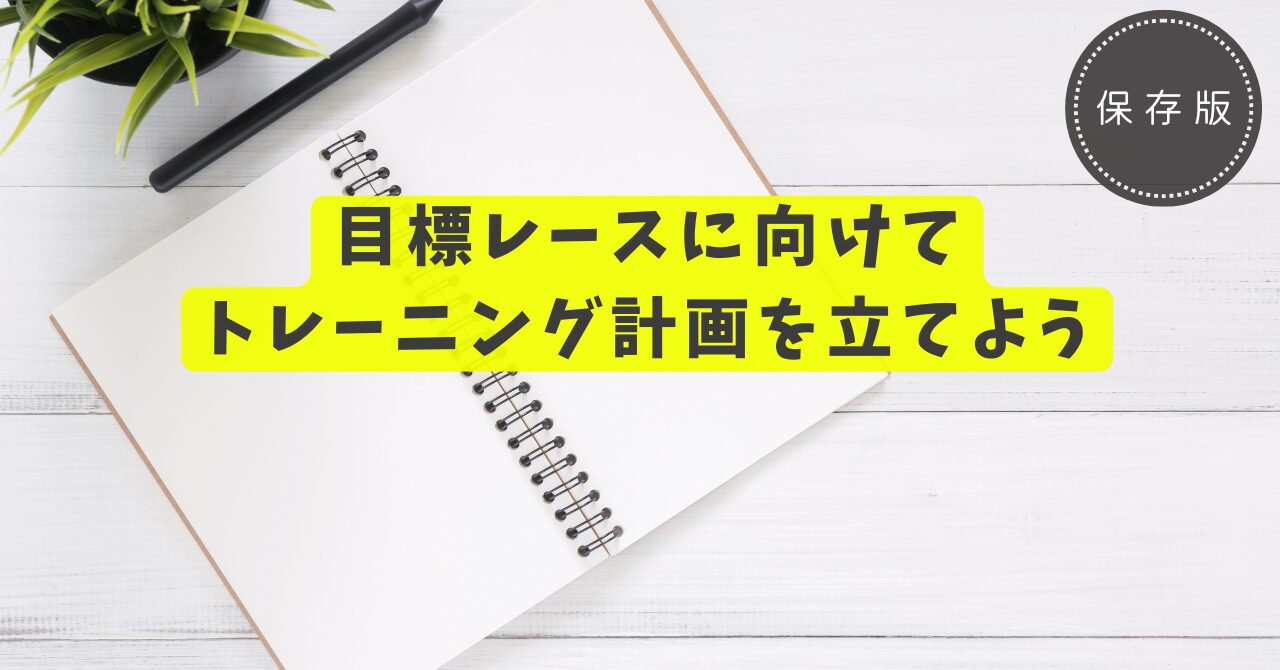


コメント