インターバルトレーニングの目的は何でしょうか?VO2Maxを鍛える、LT(乳酸閾値)を鍛える、あるいは解糖能力を鍛えることが挙げられます。それぞれの目的に応じてインターバルを行うと思います。
そして、インターバルトレーニングを行う際、意識すべきことは何でしょうか?おそらく多くの人が、疾走区間のペースをどう設定するかに焦点を当てていると思います。しかし、インターバルトレーニングにおけるリカバリー区間の過ごし方こそ、練習の肝といっても過言ではないほど重要です。
この記事では、インターバルトレーニングにおけるリカバリー区間の重要性について解説します。この記事を参考にして、ぜひインターバルの効果を最大化してください。
・リカバリーを使い分けて狙った効果を得よう
リカバリーの種類
まず、インターバルトレーニングにおいて、リカバリーの方法は大きく2つに分類されます。
- 一定時間のリカバリー(例:10x500mで30秒のリカバリー)
- 一定距離のリカバリー(例:15x200mで200mのジョギング)
① 一定時間のリカバリー
一定時間のリカバリーの場合、リカバリー中の動作(立つ、歩く、ジョギング)は各自で自由に決めることができます。この方法は、トラック練習でない場合でもインターバルトレーニングを実施しやすくする利点があります。また、リカバリー時間も調整可能です。たとえば、上記の「10 x 500m」では、最初は30秒のリカバリーを設定し、練習がきつくなった場合には、40秒または45秒にリカバリー時間を増やすことができます。
② 一定距離のリカバリー
一定距離を走るリカバリーは、トラック練習でよく使用される方法です。たとえば、200mのインターバル後に200mのジョギングを行うことが一般的です。この方法でも、練習がきつい場合には、ジョギングのペースを落とすことで、次の疾走時に良いフォームを維持できます。
リカバリー方法の詳細
次に、リカバリー方法を詳しく見ていきましょう。
① その場でのリカバリー
インターバル中にその場で休むこともありますが、立っている状態とゆっくり歩いている状態の代謝コストの差はそれほど大きくありません。むしろ、「筋肉のポンプ作用」によって血流を促進するためには、立っているよりも歩く方が効果的であり、結果的に歩いた方がリカバリーが速くなります。そのため、その場で立ち止まるだけのインターバルはあまりお勧めできません。
② ウォーキングリカバリー
ウォーキングリカバリーは、回復を速めつつ、トレーニングでの走行距離を最小限に抑えたい場合に最適です。例えば、怪我をしやすいアスリートや、すでに走行距離が多い日のトレーニングで効果的です。ただし、有酸素運動による追加のメリットは得られない点が欠点です。
③ ジョギングによるリカバリー
ジョギングによるリカバリーは一般的に使用されている方法で、リカバリー中に有酸素運動を追加することができます。ただし、リカバリーのペースが速くなるほど回復は遅くなり、無酸素エネルギーの再生が少なくなります。そのため、必要なトレーニング効果を得るためには、リカバリーのペースを適切に設定することが重要です。
また、ハイスピードのスプリントや、5000mより速いペースのロングインターバルでは、無酸素エネルギーを大量に再生する必要があるため、ジョグによるリカバリーは適さない場合があります。
④ 速いペースでのリカバリー
速いペースでのリカバリーは、乳酸をエネルギーに変換するために適した筋肉の代謝状況を作り出します。例えば、LT2ペースで1km走る、またはマラソンペースで2~3km走ると、血液と筋肉内の乳酸レベルが上昇します。リカバリー中も強度が高いと、体はこの乳酸を酸化してエネルギーを得るように働きます。
リカバリーを使い分ける
以下の2種類に分けられます。
① LT2、CV(心肺能力)を超える強度(VO2Max、Iペース)でのインターバルトレーニング
② LT2に近い、またはわずかに低い強度でのインターバルトレーニング
それぞれのトレーニングでリカバリーの目的が異なります。
① LT2、CVを超える強度(VO2max,Iペース)でのインターバルトレーニング
LT2やCVを超える強度で走っていると、VO2はVO2maxに近づき、心拍数はHRmaxに向かい、血中乳酸値が増加します。このようなトレーニングでのリカバリーの役割は、これらの値を下げ、疲労の限界に達することなく次の本数を繰り返すことです。疾走スピードが上がるほど無酸素エネルギーの消費も増えるため、リカバリー時間を適切に調整することが求められます。
② LT2に近い強度でのインターバルトレーニング
マラソンやハーフマラソンランナー向けでは、回復が早いインターバルトレーニングを使用し、乳酸を有酸素エネルギーとして利用できる生理学的状態を作ることが効果的です。このトレーニングでは、速筋線維における乳酸産生の上昇、遅筋における炭水化物の酸化率の上昇を促進します。
リカバリーにゆっくりとしたジョギングやウォーキングをすると、筋肉のエネルギー源として脂肪が利用されるようになるため、速いペース(疾走区間の85~90%)で走ることが効果的です。
このように、それぞれのインターバルによってリカバリーの方法を変えることで、正しい効果を得ることができます。
インターバルトレーニング例
具体的なインターバルトレーニング例を紹介します。
1. 10kmのペースで12x500m、25秒のウォーキングリカバリー
これはインゲブリクセンが実施しているような二重閾値走における午後のトレーニングに該当します。血中乳酸値と心拍数を安定させるため、回復時間をできるだけ短くしますが、その短い時間でできるだけ多くの回復を促すことも重要です。また、朝昼の二部練習を行う場合、その日の走行距離がかなり長くなるため、余分なランニング量を積み上げないよう、回復時間はウォーキングにすることが推奨されます。
2. 800mのペースの105%で6x300m、4分間のウォーキングリカバリー
これは800mランナー向けの「特異的スピード」トレーニングです。速いペースでの繰り返しによって無酸素エネルギーが急速に消費されます。最初の1セットを終える頃には、無酸素エネルギーの大部分が失われている可能性があります。無酸素パワーが大きく必要となるため、リカバリーをジョギングにしても、回数を重ねると必要なペースを維持できなくなることがあります。
3. 10kmのeasy run + 3セット:5kmの88-90%ペースで2km、400mをeasyからmoderateペースでリカバリー
このトレーニングでは、後半を一気に(5kmの90%ペースで6km)走るのは難しいため、2kmずつ分けて走ることで実行可能になります。さらに、easyからmoderateペースでリカバリーを入れることで、2kmの疾走区間が速くなりすぎるのを防ぎます。結果的に、17kmほど走ることになり、全体としてLT1~LT2の強度でトレーニングを行うことができます。
4. 8セット:マラソンの105%ペースで1km、マラソンの90%ペースで1km
これは変化走のトレーニングで、レナト・カノーヴァのトレーニングにも多く見られます。乳酸の酸化に非常に効果的です。さらに、このトレーニングは次のように発展させることができます。
ボリュームアップ(10 x 1k / 1k)
距離を伸ばす (5 x 2k / 1k)
より速いリカバリー (105% MP で 8 x 1k / 95% MP で 1k)
この中でも、3つ目のトレーニングは非常に高度な内容です。しかし、マラソンペースに近いペースで走りながら回復する能力は、マラソンにおいて非常に重要な能力となり、この種のインターバル(8~10x1km/1km)を96~97% MPでリカバリーを行いながら実施できれば、マラソンに向けた体力が非常に優れていると言えます。
逆に、このトレーニングを試してみて、リカバリーに90% MPでもきつすぎると感じた場合は、85%または80%にリカバリーを下げて実施し、その後、少しずつリカバリー速度を上げていくことをお勧めします。
まとめ
インターバルトレーニングでは、疾走区間のペースだけでなく、リカバリーの取り方も重要です。疾走区間の強度に応じて、リカバリー方法を使い分けることで、効果的なトレーニングが実現できます。次回のインターバルトレーニングを計画する際には、リカバリー区間を含めて最適な方法を選んで、より良い結果を目指しましょう。
【参考】
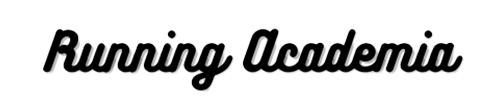
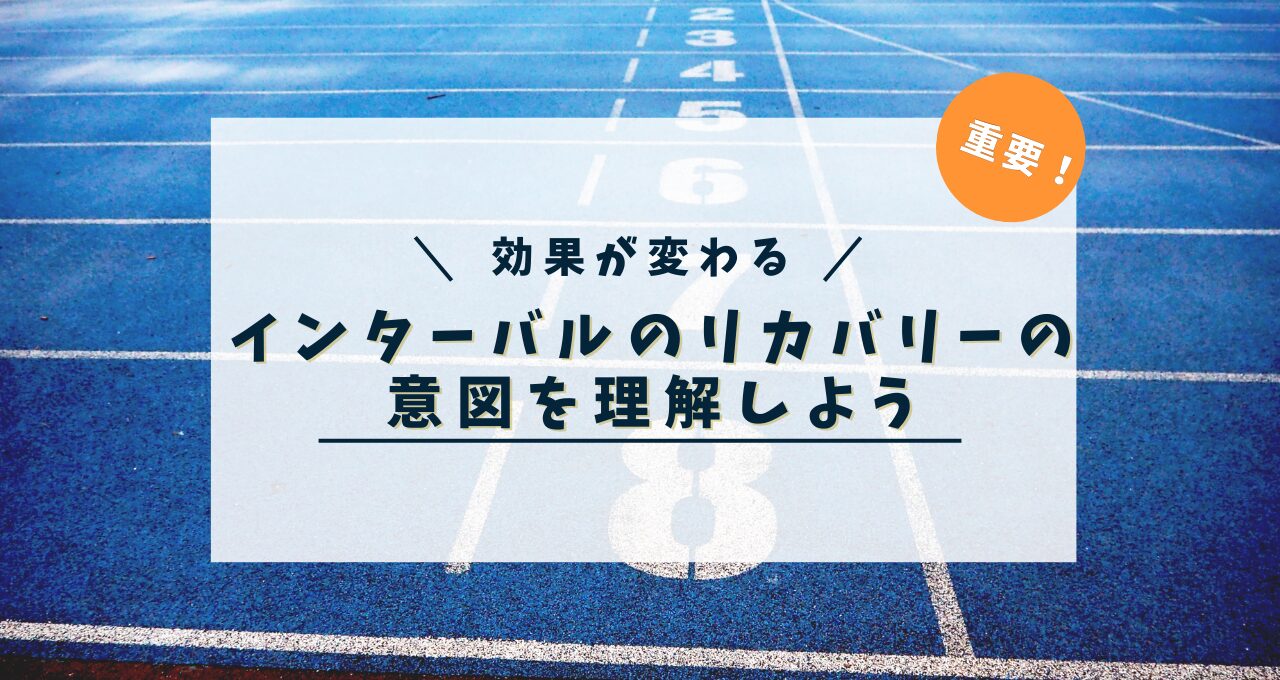


コメント