ランニングのトレーニング後に行う「クールダウン」。あなたはこのクールダウンを、ただのルーティンとして行っていませんか?実は、クールダウンにも目的意識と正しい知識が必要です。
この記事では、クールダウンの必要性や効果、避けるべき場面、トレーニングの種類に応じた具体的なクールダウンのやり方を解説します。「正しいクールダウン」でケガのリスクを減らし、トレーニング効果を最大化しましょう。
クールダウンとは何か?その役割と注意点
クールダウンとは、トレーニング後に身体を徐々に落ち着かせる目的で行う軽い運動(主にジョギングやストレッチ)のことです。
多くのランナーが「乳酸を取り除く」「疲労を抜く」といった目的で行っていますが、忘れてはいけないのは、クールダウンも“走行距離”に含まれるということです。
ランナーのケガの多くは「着地衝撃」によって起こります。無計画なクールダウンで走行距離を増やしてしまうと、かえってケガのリスクが高まる可能性があります。
クールダウンの効果とは?
クールダウンによって得られる主な効果は、血中乳酸濃度を速やかに低下させることです。特に高強度インターバルトレーニングの直後に軽いジョギングを行うことで、体内の血流が維持され、乳酸の代謝が促進されます。
実際、「アクティブリカバリー」として知られる10〜15分程度の軽いクールダウンは、ワークアウト後の乳酸レベルをより早く正常値に戻す効果があるとされています。速いペースのインターバルを行った後は、こうした軽めのジョグを取り入れることで、回復促進と筋疲労の軽減につながります。
一方で、マラソンペースやクルーズインターバルのような有酸素系のトレーニングを行った後のクールダウンには、それほど大きな効果は期待できません。これらのトレーニング自体が十分な有酸素刺激を含んでいるため、追加でジョグを行っても、それ以上の効果は得られにくいのです。実施する場合でも、数分の軽いジョギングで十分といえるでしょう。
また、既に長時間・長距離のトレーニングで脚に大きな負荷がかかっている状態では、無理にクールダウンを追加することでケガのリスクが高まる可能性もあります。目的がはっきりしない長めのジョグは避けるのが賢明です。
クールダウンを取り入れるかどうかは、その日のワークアウトの目的と、中長期的なトレーニング戦略の両面から判断することが大切です。
有酸素刺激が目的でない高強度トレーニングの後には、アクティブリカバリーとしてのクールダウンを積極的に活用。
逆に、すでに有酸素刺激を十分に得ている場合は、無理にクールダウンを行う必要はありません。
クールダウンで走行距離を稼ぐべき人とは?
特に初心者ランナーや走行距離を増やしたい時期は、あえてクールダウンジョグで距離を稼ぐという選択肢も有効です。
ただし、以下の点に注意しましょう
無理に距離を伸ばさない
疲労が強い日は短めに
フォームが崩れていないかチェック
クールダウンが逆効果になる場合
「クールダウンもトレーニングの一環」と考えて、10km以上のジョグを行う人もいますが、これは要注意です。
疲労が溜まっている状態での長いジョグは、筋や腱に強い負荷がかかり、ケガのリスクが急増します。また、有酸素刺激が目的の日とハードなワークアウトを混同すると、トレーニング効果が分散しがちです。
効果的なクールダウンの実例とその目的
① VO₂maxインターバル(例:1200m × 5本)
ワークアウトの目的:
最大酸素摂取量(VO₂max)の向上を目指す高強度トレーニング。
筋中に多くの乳酸が発生し、神経・筋系への強い刺激が入る。
クールダウンの効果:
・乳酸の代謝促進による回復スピードの向上
・血流の維持により、筋肉に酸素と栄養を届ける
・筋疲労や張りの軽減により、次のトレーニングへの影響を最小化
おすすめのクールダウン方法:
・最初の10分は「イージーペース(会話ができる程度)」でゆっくりと走る
・その後の10分は「リラックスしたペース」でさらに落とす
・合計15〜20分以内で終了するのが理想
② 高強度インターバル(例:400m × 5本)
ワークアウトの目的:
速筋線維の動員、無酸素能力の強化、乳酸産生能力の向上など。
クールダウンの効果:
・過剰に蓄積された乳酸の排出促進
・急激な心拍数の低下を防止し、循環系の負担を軽減
・神経系の興奮状態を段階的に落ち着かせる
おすすめのクールダウン方法:
・とにかく「ゆっくり」ペースで15〜20分程度のジョギング
・深呼吸を意識して心拍を徐々に落ち着かせる
・このトレーニングでは過度な距離を避けることがポイント
③ 有酸素系インターバル(例:1000m × 10本)
ワークアウトの目的:
持久力の向上、レースペースの習得、有酸素代謝の強化。
クールダウンの効果:
・乳酸の生成が少ないため、回復促進の効果は限定的
・脚の張りや疲労感を軽減するメンタル的なリセット効果程度
おすすめのクールダウン方法:
・5分前後の軽いジョグ、もしくはウォーキングで十分
・本来の有酸素トレーニング効果を維持しつつ、負荷を上乗せしすぎないよう注意
④ ロングラン(例:25km走)
ワークアウトの目的:
持久性向上、筋持久力の強化、脂肪代謝の活性化。
クールダウンの効果:
・乳酸はほとんど発生しないため、生理的メリットはほぼなし
・脚にかかる衝撃ストレスが大きいため、ジョグの継続はリスク
おすすめの対応:
・クールダウンジョグは不要
・その代わり、ストレッチやアイシングなどの静的リカバリーを重点的に実施
補足:クールダウンを選ぶ基準は?
乳酸が多く生成されたか? → クールダウンは「必要」
脚への負荷がすでに大きいか? → クールダウンは「控える」
その日のトレーニングの目的が有酸素刺激かどうか? → 必要性を見極めるポイントになる
まとめ|その日の目的に応じてクールダウンを選ぼう
「トレーニング後はとりあえずクールダウン」という一律のルールではなく、その日のワークアウトの目的を明確にし、クールダウンの必要性を判断することが大切です。
高強度トレーニングの後は積極的にクールダウンを
有酸素刺激が主目的なら、控えめ or 不要
ケガのリスクを常に意識して距離と内容を調整
正しいクールダウンの実施で、あなたのランニングパフォーマンスとコンディションを長期的に向上させましょう!
効果的なクールダウンの実施について
クールダウンを行うにあたり、どのようなワークアウトと組み合わせると良いか、いくつかの例を示します。
①5×1200mのようなVO2maxペースでのインターバル
このようなペースでのインターバルでは乳酸がある程度生成されます。その状態でのクールダウンは乳酸の再処理が促され、筋疲労の改善につながります。また、クールダウンの最初はイージーペースくらいで実施することで、乳酸除去能力への刺激(閾値刺激)が入り、とても効果的なものになります。10分ほどイージーペースで走り、残り10分はゆっくりと走ると良いでしょう。
②800mペースのような高強度インターバルの後のクールダウン
大量の乳酸が血液中に溜まった状態になるため、かなりゆっくりとしたペースで15分~20分程度のジョギングにしておきましょう。ここでのトレーニングの目的はは乳酸を生産する能力の向上です。有酸素能力の向上とは異なる練習なので、混ぜないようにしましょう。長すぎるクールダウンはインターバルの効果が薄れてしまうので、気をつけましょう。
②1000m×10のようなハーフマラソン向けの練習後
このような練習では、乳酸はそれほど生成されません。ワークアウト自体が有酸素運動であるため、クールダウンの効果はあまり期待できません。走行距離を増やすために走ることもありますが、短時間で終わるのが重要です。
③ 25kmほどのロングラン
マラソンに向けたロングランでは乳酸はほとんど生成されず、脚への負荷も高く、かなり大きな有酸素刺激が身体に入っています。これだけの距離を走った後のクールダウンのメリットはほとんどありません。ロングランの後はすぐにリカバリーを行いましょう。
まとめると、乳酸が大量に生産されるような練習後は15分程度のクールダウンを取り入れることで、乳酸除去が促されます。また、VO2max付近の強度ではクールダウンのペースをイージーペースにすることで、乳酸酸化能力の向上が見込まれます。
一方で、ハーフマラソンやマラソン練習のような有酸素刺激がメインの練習後はクールダウンはほとんど必要ありません。
すでに足への負荷が高くなった状態でのクールダウンは、得られるメリットよりもケガのリスクが大きくなるため、控えめにしておきましょう。
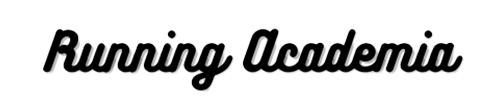
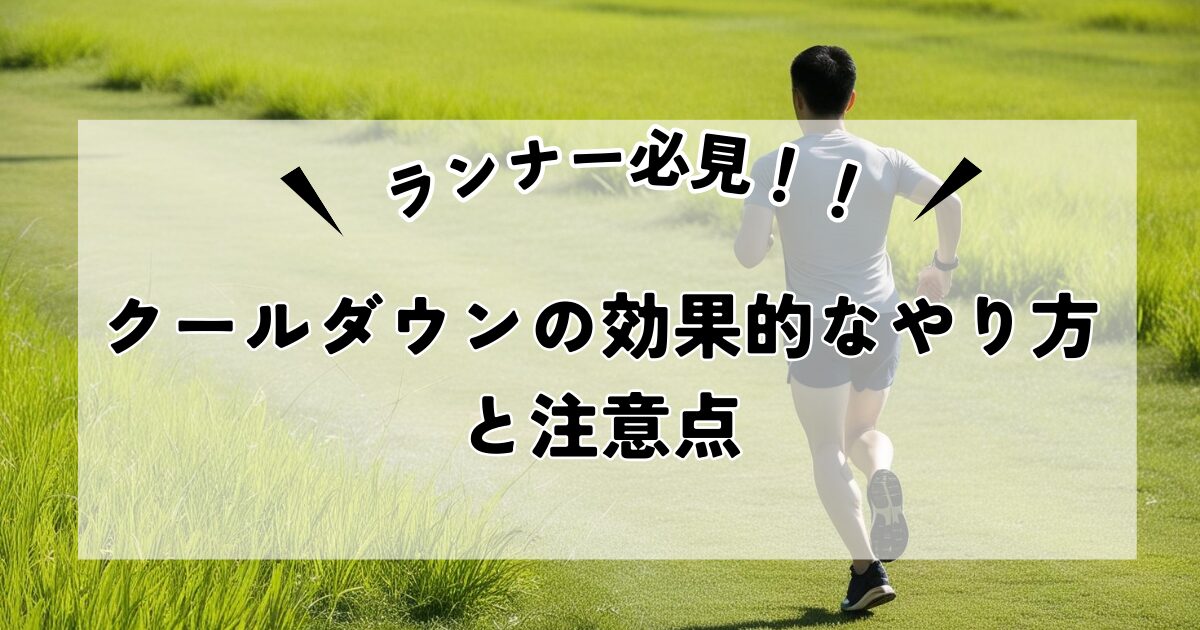


コメント