陸上トレーニングを調べていると、よく「解糖系」という言葉が出てきますが、正確には「解糖」と呼ばれます。この仕組みについて、名前だけではピンと来ない方も多いかもしれません。「糖を分解する仕組み?」、「鍛えるとどうなるの?」という疑問を解消するために、解糖の仕組みや働きについて詳しく説明していきます。
・解糖はどんなときに働くのか
・解糖を鍛えるとどうなるのか
細胞呼吸の3つのステップ
解糖系とは、身体の代謝システムの一部であり、ヒトは細胞内でグルコースを酸素を使って分解し、エネルギーを取り出します。この過程を「細胞呼吸」と呼び、二酸化炭素や水が発生します。
細胞呼吸は、以下の3つのステップに分かれています。
解糖系
クエン酸回路
電子伝達系
1.解糖系
解糖系では、グルコースがピルビン酸という物質に分解され、この過程で少量のエネルギーが取り出されます。この反応は、細胞質基質という部分で行われます。細胞質基質は、核や細胞小器官以外の部分を指し、さまざまな酵素が反応を促進します。
2.クエン酸回路
解糖系で生成されたピルビン酸はミトコンドリアに運ばれ、すべて二酸化炭素に分解されます。このときも少量のエネルギーが取り出されます。
3.電子伝達系
ここでは、水素イオンが移動することで大量のエネルギーが生成されます。余分な水素イオンが酸素と反応し、水として排出されます。この段階でのみ酸素が必要となり、酸素を使って水が生産されます。
これら3つのステップを経て、グルコースからエネルギーが取り出されますが、トレーニングで言われる「解糖系」とは、実はここでの「解糖系」とは異なり、正しくは「解糖」と言います。解糖系と解糖は似ているようで、実際には違いがあります。
解糖系と解糖の違い
「解糖」とは、グルコースが分解されて生成されたピルビン酸を、ミトコンドリアで分解せずに乳酸に変える反応を指します。この過程では酸素は使われません。乳酸菌が行う乳酸発酵と同じ反応です。ヒトの筋肉でこの反応が起こる場合を「解糖」と呼びます。解糖によって乳酸が生じ、エネルギーが供給されます。
運動時のエネルギー供給のしくみ
生物はエネルギーをATPという物質として蓄えており、ATPを分解したときに発生するエネルギーを活動に利用します。エネルギー源としてグルコース(=糖)を使いますが、グルコース自体を分解してすぐにエネルギーとして使うわけではありません。グルコースを分解して生じたエネルギーでATPを合成し、そのATPを分解することでエネルギーを取り出して活動します。
*つまり、一度ATPを介さないと我々はエネルギーを利用できません。
CP-ATP系
筋肉でもATPを使って筋収縮が行われますが、筋肉内にあるATPは数秒で枯渇します。そのため、消費したATPを素早く再合成する必要があります。この過程で、筋肉内のクレアチンリン酸(CP)を分解してATPを再合成します。これがCP-ATP系と呼ばれるエネルギー供給システムです。この分解によって供給されるエネルギーで筋肉は約15秒間収縮を持続することができます。
解糖
ミトコンドリアでの酸素を使った代謝反応が始まる前に、クレアチンリン酸が枯渇すると、次に解糖によってATPが合成されます。この反応によって、約30~40秒間筋肉が最大収縮を維持できます。それ以上の運動では、呼吸によるATP合成がメインとなります。
つまり、100mのように短時間で終了する運動はほとんどがCP-ATP系によってエネルギー供給されます。400mのような中距離になると、CP-ATP系と解糖によるエネルギー供給が行われます。この解糖によるエネルギー供給が得意な選手ほど、1分程度の運動においてパフォーマンスが高くなると言えます。
呼吸
1分以上の運動では、エネルギー供給のメインは呼吸によるATP合成となります。グルコースが分解されて生じるピルビン酸や、解糖で生じた乳酸はミトコンドリアで処理され、エネルギー源となります。ミトコンドリアの数が多いほど、乳酸を効率よく処理でき、エネルギー供給も効率的になります。
この反応によるエネルギー供給が最も多く(解糖の19倍)、生命活動に必須のしくみとなっています。
このように、3つのエネルギー供給経路があるのですが、運動時間によって3つの経路のうちどれか一つのエネルギー供給のみが起こっているというわけではなく、供給割合が変化しているというのが正しい認識になります。
乳酸をうまく使う
解糖によって生じた乳酸は、今やエネルギー源として再利用できることが知られています。乳酸は筋肉で生成された後、肝臓に運ばれ、1/5が完全に分解されATP合成に利用されます。残りの4/5はグリコーゲンに再合成され、再びエネルギー源となります。
乳酸を素早くエネルギーとして再利用できれば、高い強度を維持したまま、長時間の運動が可能になります。
解糖能力を鍛えるとどうなる?
運動に必要なエネルギーは、CP-ATP系、解糖、有酸素系(呼吸)によって供給されます。CP-ATP系はすぐに枯渇するため、運動開始後は解糖と呼吸によってエネルギーが供給されます。
解糖能力が高い選手は、乳酸を大量に生成でき、短距離から中距離の運動でパフォーマンスが向上します。また、長距離選手も解糖能力を活かし、呼吸による供給が間に合わないエネルギーを補うことができます。しかし、乳酸を効率よく除去できなければ、筋肉が酸性になり、筋収縮が妨げられるため、パフォーマンスを維持できなくなります。したがって、長距離選手は乳酸を酸化して除去する能力を鍛えることが重要です。
解糖能力を鍛えるには?
解糖能力を鍛えるためには、乳酸を大量に発生させる練習が効果的です。たとえば、400mのレースでは300m付近が乳酸の最大値だとされており、300m×5のようなレペティション練習が解糖能力を高めます。この際、リカバリーは十分に取ることが重要です。リカバリーが短いと乳酸が十分に除去されず、2本目以降で十分な効果を得られません。解糖能力で重要なのは、しっかりと乳酸を作り出すこと。リカバリーを十分に取って、レペティションに取り組んでみてください。
また、解糖は筋肉で起こる反応なので、筋肉量を増やすことも重要です。自分の種目に合った筋力トレーニングを取り入れましょう。
おわりに
もう一度おさらいします。
- よく言われる「解糖系」とは、実際には「解糖」と呼ばれる筋肉内での代謝反応のこと。
- 「解糖」では、筋肉内でグルコースが分解されて乳酸が生成される。
- 「解糖」の能力を鍛えると、400m前後の距離でのスピードが向上する。
陸上競技において、一つのシステムだけを鍛えることではなく、どの能力を改善したいのかを理解して効率よくトレーニングを行うことが重要です。練習の目的をしっかりと理解し、効率よく力を伸ばしていきましょう!
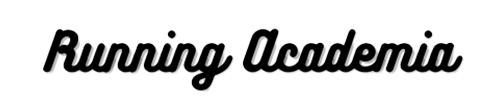
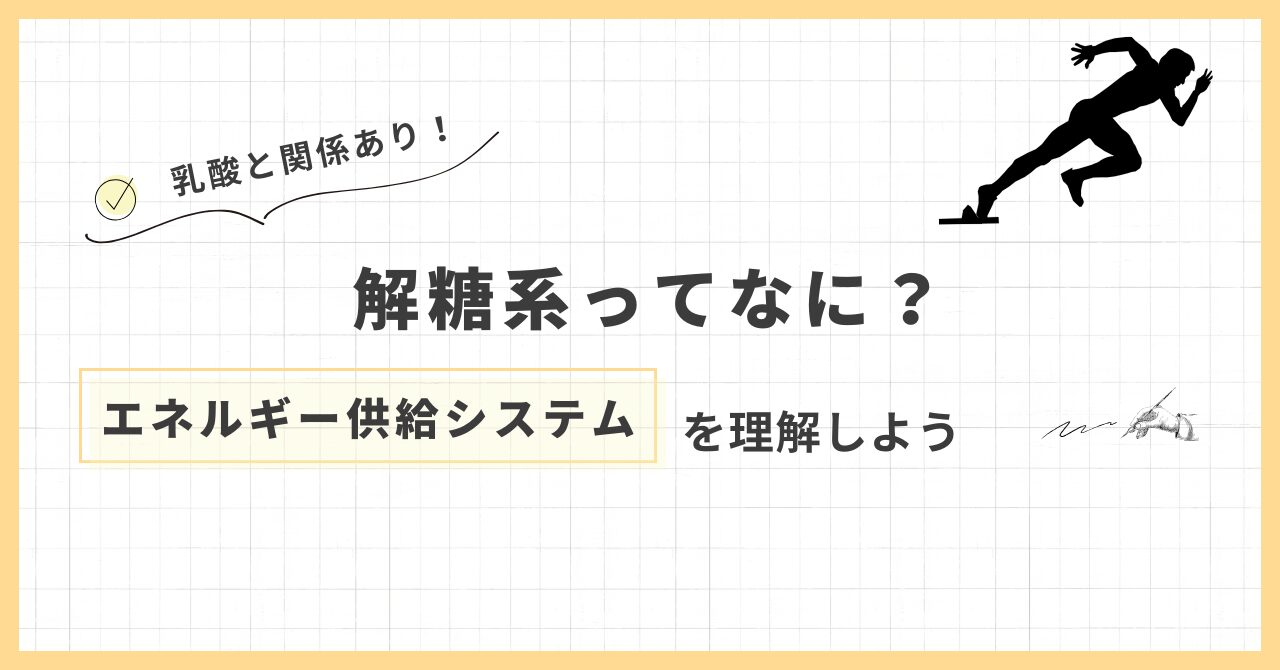
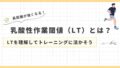
コメント